Log.1 - 船上の記憶
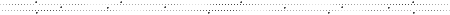
「……参ったな」
大きな船の甲板の上。淡い蒼色の髪をした男が面倒くさそうに呟く。白のメッシュの入った長い前髪は簡単に左右に分け、小さく丸いレンズのサングラスを掛けている。服装はスーツだが派手なワインレッドだ。
――海上を行き交うカモメの群れと、堂々として浮かぶ白い雲を眺める。
周囲にちらほらと見える客の表情は皆嬉々として――否、むしろ闘争心に燃えている者も多く殺伐としているとも言えそうだった。
そんな中でただ1人、先ほどの無気力男がぼーっと海を眺めている。
何も望んで無気力でいる訳ではない、状況がそうさせているのだ。
そう自分に言い聞かせながら、これから先のことを考える。
「はぁあ」
ため息と共に少し背伸びをした、その時だった。
――カランッ
「あ」
落としてしまった。失くして困る訳ではないが、出来れば失くしたくは無い――着の身着のままやってきた彼にとって、唯一の持ち物がそれだった。
それは傾いた甲板の上を簡単に転がっていく。慌てて追いかけるがなかなか追いつけない――……、と。
歩いてきた誰かの靴に、それが引っ掛かった。靴の主はすぐそれに気付き拾い上げると、彼に向かって表情を変えずに問い掛ける。笑顔ではないが、嫌な感じはしなかった。
「貴方のですか?」
「あ、ええ――ありがとうございます」
「いえ。それでは、先生」
靴の主は長い茶髪を風になびかせながら、またゆっくりと歩いて何処かへ行ってしまった。
(ど……どうしてコレが教鞭だとすぐに)
この船に乗っている客の持ち物としてはおおよそ相応しくないと言うのに。
彼が木の棒にしか見えない物体を手に持ってぼーっとしていると、背後からゆっくりと何者かの影が近付いてきた。
「こんにちは」
「え?あぁ……こんにちは」
振り返った先に立っていたのは、紅い髪をポニーテールにした、赤縁眼鏡の女性だった。歳は彼と同年代のように見える。
「貴方もお金目当て?それとも誰かさんの追っかけかしら」
「え」
追っかけと言えば追っかけ――なのかも、知れないが。
彼女が言いたい意味とは少し違うような気がして、どうも肯定しかねる。
「っと……なんちゅうかな……こう……」
「まぁ追っかけでも何でもいいわ。この船に乗ってるからには皆事情があるんでしょーし。初めまして、私は紅月と言います。貴方は?」
「あぁ、どうも――陽月です、よろしゅうに」
「ふぅん、陽月先生ね。憶えたわ、ありがと。島に着いたらよろしくね」
紅月はにこにこと笑いながら陽月の腕をぱしぱし叩いて言った。
何ともいきなり馴れ馴れしいと言うか――遠慮がない。
「な、何で俺が教師やとすぐに」
「え、ああほら、さっき彼が――」
「彼?」
きょとんとした顔で、紅月は陽月の後ろを手で示した。ゆっくりと振り返ると、先ほどの男はすぐ傍まで近寄ってきていた。変わった服を着ている。東洋系の血を感じさせる顔立ち、さらさらと流れるような栗色の髪、細い目は冷徹そうに見えてそうでもない――。
「さっき知り合ったんだけどね」
「ユラギと言います。驚かせてしまったようですみません。特に根拠は無かったのですが、お名前も存じませんし、何となくそんな感じがしたもので咄嗟に先生と――」
男が苦笑する。近くで見ると陽月より少し背が高い。
「何となく、て……」
「ユラギ君は医者なの。頭良いのよ」
関係無いような気がしたがツッコミはやめておく。
「止めて下さい、昔の話ですから――。今は呪術師としてここに来ています。ほら」
ユラギと呼ばれた男は赤い玉のついた大きな杖を見せてくれた。いかにも魔法使い――である。
「なるほど、呪い師さんか」
「ええ。――でも紅月さんだって、考古学博士号を史上最年少で取ったってさっき言ってたじゃないですか」
「へぇ……考古学者やったんか」
少し意外だったが聡明そうではある。
いきなり自分の話題になった紅月は一瞬またきょとんとした顔を見せたが、すぐに強気な表情に戻った。
「そう、島には発掘に行くの。――堂々とそんな事は言えないんだけどね。あの島には何かあるのよ、絶対。何にも言わないで死んじゃうなんて、頭おかしいんだわあのオジサン」
「言い過ぎると良くないですよ、誰かの耳に入ったらどうするんです?」
「……そうね」
紅月は咳払いをしてごまかした。話は勝手に進んでいった。
陽月はその『島』だとか『オジサン』だとかが一体何なのか良く判っていない。この船がカバリア島という島を目指しており、その島の所有者がドン・カバリア氏で『オジサン』なのだろうという事までは判るが、それ以上詳しい事は全く知らない。何せ授業中に教室を飛び出した彼女達を追いかけて、「カバリア島行きの船」と言う情報だけでここまで来てしまったのだから――。
「そうそう、さっき言おうとしたんだけど――追っかけが来るほどの『誰かさん』って言うのはあの緑髪のお姉さんね」
小声で陽月にそう告げると、紅月は自分達の反対側に立つ女性を示した。綺麗な黄緑色の髪が風になびく。露出度の高い服を着ているが、それが似合っているから文句は言えまい。もし紅月が同じ衣装を着ていたらどうだっただろうと想像して、一瞬吹き出しそうになった。
「?」
「え、いや、何でもない。彼女が何なん?」
「モデルさんらしいですよ。お名前までは判りませんが、何でも今度出演する映画の衣装代を稼ぎに来たとか――」
ユラギが答えた。紅月が嫌そうな顔をした。
「な、何それ、衣装代を出演者が稼ぐ訳?か……可哀想、あのお姉さん」
「紅月さん、声大きい。大体お姉さん言うてるけどな、あの人のがアンタより年下やと思うで、俺」
「ええ、そうかな」
そんな事は全く思っていないらしい。自尊心は高そうだ。だが格別嫌味な感じがする事も無い。
ユラギが少し唸ってから答える。
「そうですね――……彼女はまだ十代のような気がします」
「……歳なんてどうでもいいわ。でも……とにかく島にはあんな大物も来るって事ね。ついでに何も知らない素人も……。誰かに間違って掘り出される前に、私が一番乗りにならなくちゃ」
眼鏡の奥の瞳は真剣そのもの。ここに来てようやく、彼女が考古学者である事に納得が行った。
――船が大きく汽笛を鳴らす。
その音は彼らの前途を祝福しているようであった。
「あ、島が見えてきたわ――……わぁ、火山が見える!」
「何や、ホンマにテーマパークって感じやな」
「ゲームを舞台にしたテーマパーク……何だか想像もつきません」
「ね、陽月先生」
「ん」
「私とユラギ君は島に着いてからも一緒に行動するわ。言わば一種のパーティーね。もし良かったら、先生も一緒にどう?」
誰も知らない島の中でたった一人、情報も何も無い中で女子生徒たちを探す――……無謀、かも知れない。
それにずっと一人で居るのは少々、つらいような気もする――。
「あぁ、俺でかまへんなら、加えたってくれ」
「オッケー、これで決まりね!おふたりとも宜しく」
「改めてよろしゅう」
「宜しくお願いします」
船の進む先に、大きな港が見えてくる。人気は余り無いようだ――。
「島に着いたら動物の格好をしなきゃいけないんです、って。何にするかは決めてある?」
「え、何と言われてもやな――」
そもそもそんな事は知らない。
……大体何故だ。一体誰の趣味だろう。
恐らくはドン・カバリア氏が決めた事なのだろうが――とりあえず、恥ずかしい。
「僕はその場で決めますよ。特にこだわりも無いですし」
「まぁ……そうね。くれぐれもハズレ引かないように努力しましょ。特に何も知らなかったと言いたげなそこのお兄さん」
「ぐ」
鋭い。しかし――事実、象とかが残っていたらどうしたらいいのだろう。
その暁には自分は女子高のアイドルからカバリア島の変人エレファントに転身、などと言う事態になりかねない。
それだけは何としてでも回避したいものである。
「さぁ、降りる準備しましょうか」
もうすぐそこに見える港の広場の真ん中には、金ぴかのオジサンの像が見えた。
(アレが……ドン・カバリア?ビールジョッキ持ってるし。とりあえず相当の変人やってんな、きっと)
そうでもなければ島への入場者に動物の格好をさせるなどと言う奇態な事はしないだろう。
「陽月先生、置いてかれるよ!」
紅月の声がする。
気付けば周囲の客は既に降り口へと向かった後だった。
「ん、あぁ……今行くで」
――陽月は2人の背中を追いかけた。
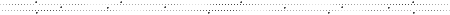
+Back ‖ Top ‖ Next+