Log.2 - 異次元の記憶
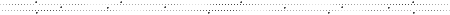
港は思いの外混んでいた。あの船には相当な数の人間が乗っていたらしい――そしてそのほとんどが、既に思い思いの場所へと旅立っていく準備を済ませていた。
「ほら、先生も早く早く!こっちで街にテレポートさせてもらえるって!」
狐の耳と尻尾を――何故か2本――つけた紅月が楽しそうに言った。
あと7本余分につければ九尾の狐とからかえたのに、と――陽月は良からぬ事を考えたがすぐに撤回した。そんな事を言ったら恐らくぶっ飛ばされる。
「テレポートか……何や凄いねんな、メガロカンパニーとやら……」
「も、ごちゃごちゃ言ってないで早く」
「……へいへい」
とは言っても陽月は最後の乗客、残っているのはごくわずかな衣装のみである。
船から降りたところに立った女性――オウムのような格好をしている――は、何を思っているのやら、ニコニコとこちらに笑い掛けている。
「……こんにちは」
「こんにちは!カバリア島へようこそいらっしゃいました!お好きな衣装を選んでくださいね♪」
何も語尾に音符まで付けられなくとも、自分に求められている行動は判っている――……しかし、目の前には明らかに『選ぶ』ほどの選択肢はなかった。
「えっと……これ……しか、無いねんな」
「は……はい、そうなりますね。他の衣装は数が足りなかったようで……」
明らかに同じものだけが残っているという異常事態に、何らかのフォローは無いのだろうか。
――とにかく、これを付けない事には中に入れない。
ここは腹を括るしかない。授業中に飛び出した生徒たちを、何としても見つけなければならないのだ。
陽月はその耳と尻尾を装備した。
「はい!とてもよくお似合いですよ、たぬ、ゴホッ、可愛いアライグマ!」
「……アンタ今何か言い掛けんかった?」
「え、何の話ですか?私は何も言ってませんよ。あ、ほら、お友達の方が呼んでますよ!」
金髪ウェーブヘアの女性――どうやらアナウンサーであるらしい――は、陽月の肩を押し、紅月たちの方に無理矢理向かわせた。
(ったく、ごまかしよって)
もっとも、だからと言ってここでゴチャゴチャと論議する意味は無い。狸であろうがアライグマであろうが関係ない。
「やーん何その尻尾ーかわいー」
紅月が笑いを堪えながら言う。
「……お前……」
「まぁまぁ、喧嘩はまた後にして……行きましょう。あそこに居る方が全員のテレポートを手伝ってくれるそうです」
ユラギが示した先には、モンスターらしき生き物を肩に乗せた青年が居た。
「……ほう」
「全員一気に飛ばすの?魔法なのかな?何にしても物凄い労力使いそうね」
「ここで働くのも大変ってこっちゃ」
「何ー何その判りきったような言い方ー」
「だから……!」
言い返そうとした瞬間、視界が揺らいだ。
こんな経験は初めてだ――……少し酔うかも知れない――……。
そんな事を考えている間に、歪んだ視界は一瞬真っ暗になったかと思うと――次の瞬間にはまた、違う景色が揺らぎ始めた。
揺れが収まる。辺りを見回すと――……そこは一面の砂漠だった。周りには誰も居ない――……?何故だろう、全員で同じ場所に飛ばされたのでは無かったのか?
と思ったその時、目の前に人影が見えた。
「誰?」
背は同じぐらいだろうか――……銀色に輝く髪を持ち、陽月と似たような服を着ている青年。付けている動物の衣装もどうやら同じ、『ラクーン』であるようだ。
青年がこちらを一瞥し、ハッとしたような顔で言う。
「……こんなところで何をしているんだ?早く――……」
そこで再び、視界が揺らいだ。
思わず目を閉じた陽月が、再び瞼を開けると――……青年の代わりに紅月が目の前に立ち、こちらの顔を覗き込んでいた。
「ウワッ」
「ウワッ、って何よウワッ、て……。どうしたの?何か1人でボーっと固まってたけど」
「固まって……?んー、いや、俺と似たようなカッコの奴に会うてん。真っ白い頭の」
「真っ白?そんな人は見てないけど……ユラギ君も見てないよね?」
「そうですね……少なくとも銀髪の男性はここに来てから見ていません」
では今のは何だったと言うのだろう――……。
「まぁ先生だって幻覚見ることもあるわよね!さて、とりあえずどうしましょうか」
紅月が陽月の肩をバンバン叩く。
「幻覚じゃ……ッ」
「いくらなんでも素手じゃなんだし、武器か何か欲しいところよね。ここ、モンスターとかも出るみたいだし」
「僕は戦闘魔法を覚えないと――」
「……最初に何か支給されるとか無いんかな?いきなりこっち飛ばしてポイか?金も船代で消えてんのに、初っ端からジ・エンドかいな、俺」
3人が3人とも考え込んでしまったところに、背後から小さく声が掛かった。
「あ、あの」
「むぉっ、何や」
そこには水色の髪をおさげにした、うさ耳付きの少女が立っていた。彼女は自らフレンチメイドだと名乗り、話を続けた。
「もし宜しければ、初心者講習会の会場に送って差し上げますよ。港の担当が何も言わずにいきなりこっちに飛ばしちゃったみたいですから……本来なら講習会に行かれる方と行かれない方を分けて、別々にテレポートさせるはずだったんですが」
「って事は向こうのミスか」
「はい――多分今頃ハンターマスター様に……あ、何でもありません。それでは……3人とも講習会に行かれますか?」
メイドがにっこりと微笑む。
紅月なら『さっきは彼女にメロメロになっちゃって』ぐらいの事は言うだろうか――。
否、無駄なことを考えている場合ではない。
「はい、よろしくお願いします!」
3人の声が初めて揃う。
「判りました、ありがとうございます。それでは行きますね――」
メイドの声だけが耳に残り、再び視界が揺らいで――。
目の前には、港で会ったアナウンサーが――……立っていた。
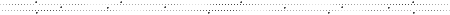
+Back ‖ Top ‖ Next+